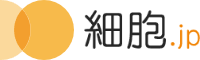研究・開発の窓 COLUMN
研究・開発の窓

新たに確立した神経変性疾患モデルラットを用いて病態メカニズムを解明
大阪公立大学大学院 獣医学研究科 准教授 田中美有氏自然発症の歩行異常ラットと出会い、発症原因を探る 大阪公立大学大学院准教授の田中美有氏(獣医学研究科獣医病理学)は、神経変性疾患の一つである神経軸索ジストロフィー(Neuroaxonal dystrophy; NAD)のモデルラットを確立し、その病態メカニズムを解明した。田中氏は動物の細胞や組織を顕微鏡で観察して病気を診断する獣医病理医として病理検査にも携わりながら、研究を続けてきた。メイン研究テーマは、「モデル動...

転写因子も創薬標的にできる新たなモダリティ「PROTAC」研究を推進
国立医薬品食品衛生研究所 有機化学部 部長 出水庸介氏ユビキチン・プロテアソーム系を利用する創薬手法 近年、注目を集める新しい創薬モダリティの一つにPROTAC(Proteolysis-Targeting Chimera)がある。国立医薬品食品衛生研究所の出水庸介氏は2010年からPROTACの研究を進め、創薬標的になりにくかった転写因子を標的とした「デコイ核酸型PROTAC」を開発するなど革新的な成果を生み出している。 PROTACは、細胞内のタンパク質分解機構であ...

新しい理論「生物力学」とAIを活用した汎用疾患予測モデルを開発
慶応義塾大学医学部 教授 桜田一洋氏(石井・石橋記念講座/拡張知能医学)臨床試験で直面した2つの課題解決を目指してAI研究者に 医学・医療分野でもAI技術の応用が進み始めたが、慶応義塾大学医学部・拡張知能医学講座教授の桜田一洋氏は、新しい理論「生物力学」とAIを活用した汎用疾患予測モデルを開発し、社会実装を目指して研究を続けている。 桜田氏は再生医療からAI・メディカルデータサイエンスに専門分野を変えた異色の研究者で、2007年にヒト細胞初期化に成功し、2011年に疾患予測のための標準...

最先端のプロテオーム解析技術を用いて、進行胃がんの新たな治療標的を同定
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 創薬デザイン研究センター 副センター長 足立 淳氏(創薬標的プロテオミクスプロジェクト)微量な臨床検体からリン酸化シグナルを解析できる技術を開発 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(大阪府)創薬デザイン研究センターの足立淳副センター長らのグループ(創薬標的プロテオミクスプロジェクト)は、最先端のプロテオーム解析技術を用いて治療標的やバイオマーカーを探索する研究を続け、進行胃がんや大腸がん肝転移の新たな治療法などにもつながるいくつかの成果を生み出している。 創薬標的プロテオミクスプロジェクトの目...
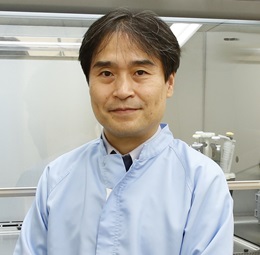
研究機関の培養細胞の4分の1が
マイコプラズマに感染、定期的な検査が必須
医薬基盤・健康・栄養研究所 創薬資源研究支援センター長 小原有弘氏2007年全国調査で細胞のマイコプラズマ汚染率は26% 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の創薬資源研究支援センターは、JCRB細胞バンクの運営と細胞の品質管理法などの開発研究を行っている部門である。センター長の小原有弘氏は「細胞の品質管理で特に問題になるのは、目に見えない、顕微鏡でも分からない汚染やコンタミネーションであり、その代表例がマイコプラズマとウイルスの感染、細胞同士のクロスコンタミネーション(入...
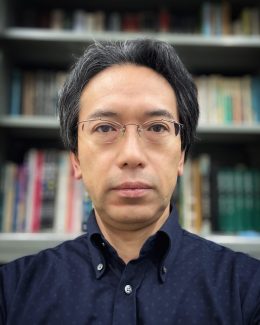
薬物動態を解析するマルチ臓器モデルとMPSの冷蔵流通技術の開発を推進
群馬大学大学院 理工学府 教授 佐藤記一氏MPS開発の鍵は細胞で構成する界面の再現 近年、創薬研究の動物実験代替手法としてMPS(Micro physiological System=生体模倣システム)が注目されている。群馬大学大学院教授の佐藤記一氏(理工学府・分析化学研究室)は薬物動態解析のためのMPS開発を目指す研究者だ。腎臓や腸管などの単独臓器モデルと複数の臓器モデルを連結した生体モデルの開発を進めるとともに、産業化を前提にMPSの冷蔵流通技術開発に...